

よく考えて進んで学ぶ子
思いやりのある心豊かな子
力いっぱいがんばる子

校長室よりお便り 校長室へ戻る トップページへ 前ページへ 次ページへ


よく考えて進んで学ぶ子
思いやりのある心豊かな子
力いっぱいがんばる子

本のある環境を
校長 稲 塚 繁 樹
|
阿星の山が 晴れている |
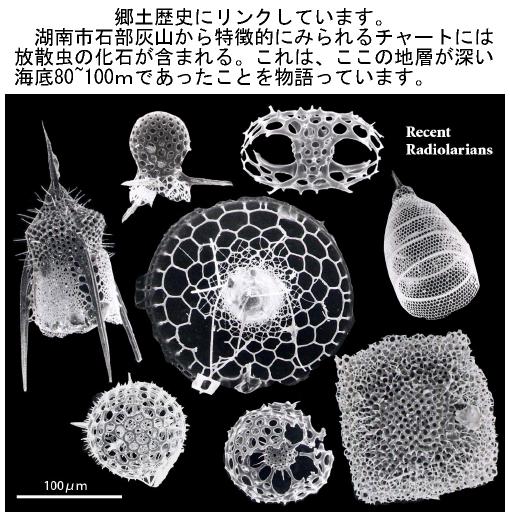 |
前号でもお知らせしたように、本年度は、書く力を育てるとともに 読む力の育成 に力を入れたいと考えています。
読む力を育てる活動の中で、大切にしていきたいのが、「読書」です。 読書の効果とは、どのようなことでしょうか。
読書は豊かな感性と考える力を育み、人生をより深く生きていくために欠かせないもので、学力向上等の教育効果があると実証されています。
国立青少年教育振興機構が「子供のころの読書習慣は大人になってからどう影響する?」という調査をしています。 そのなかで、高校生・中学生を対象にした青少年調査から、このような結果(抜粋)が出ています。
『就学前から中学校時代までに読書活動が多い高校生・中学生ほど「未来志向」「社会性」「自己肯定」「意欲・関心」「文化的作法・教養」「市民性」「論理的思考」のすべてにおいて、現在の意識・能力が高い。 特に、就学前から小学校低学年までの「家族から昔話を聞いたこと」「本や絵本の読み聞かせをしてもらったこと」「絵本を読んだこと」といった読書活動は、現在における「社会性」や「文化的作法・教養」との関係が強い』など、読書の効果を示しています。
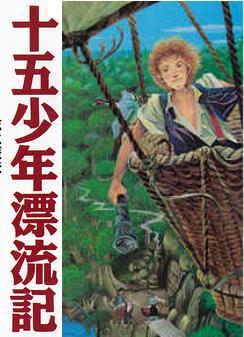 |
私が小学時代に読んだ本の中で、今も記憶に残っているのが、学校の図書室で借りた「十五少年漂流記」です。 『6週間の楽しい公開旅行に行くはずの少年たちだったのですが、少年たちだけを乗せたまま船が港を流れ出し、 漂流してしまうのです。そして、激しい嵐に巻き込まれ、無人島にたどり着きます。そこで様々な事件が起こる。』 という冒険物語です。 自分自身が冒険の旅に出たような気持で、次はどうなるのか、 ハラハラ・ドキドキしながら、ぺーじをめくって いました。 作者ジュール・ベルヌは、「80日間世界1周」「海底二万海里」などの空想冒険小説を多く書いています。 |
学校でも読書の効果を高めるために、「朝の読書」に取り組んでいます。 また、学校図書館の充実や学校図書館協力員さんの活用・教師やボランティヤさんによる読み聞かせなどの取り組みをしています。