.jpg)
.jpg) 古代の石部
古代の石部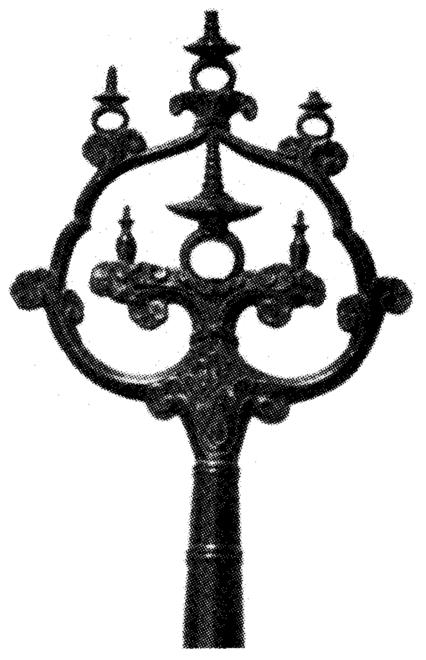
石部南小学校ホームページへ 総合目次へ 郷土歴史はじめへ
総合目次検索へ 石部の自然環境検索へ 古代の石部検索へ 中世の石部検索へ 近世の石部検索へ 近・現代の石部検索へ
200000000
.jpg)
.jpg) 古代の石部
古代の石部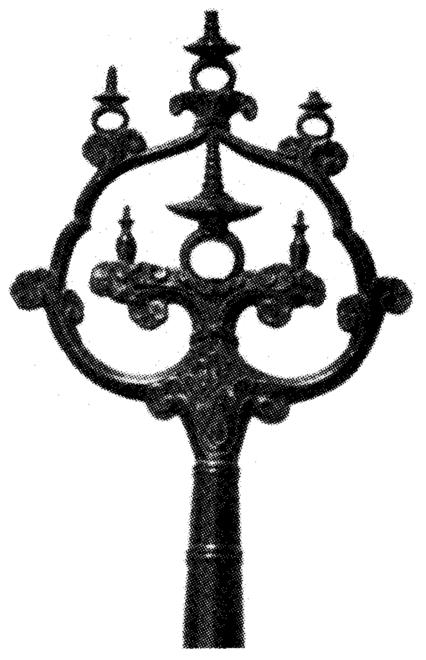
203000000 第三章 平安時代の石部
203040000
第四節 仏教文化と神道美術
定朝様の仏像
203040201
定朝様式の成立 寄木造の大成者である仏師定朝は、仏像彫刻における新様式の確立者でもあった。かれのせいさくであることの確実な現存作例は、天喜元年(1053)に供養された宇治平等院鳳凰堂の本尊阿弥陀如来坐像(国宝)一躯のみであるが、貴族達の注文が彼に殺到して多数の造像に従事したことは諸種の文献に明らかである。彼の創始した平明で静的・絵画的な様式が、それだけ藤原貴族の好尚にかなったわけだが、とりわけ観想の対象となる阿弥陀仏の姿としてふさわしい像容ではなかったかと思われる。鳳凰堂像に代表されるこの定朝様は、運慶・快慶らの登場によって鎌倉新様式が成立するまでの一世紀以上もの間、まさに一世を風靡した感がある。なかには定朝の制作した像の精密な法量を測定し、可能なかぎりこれを模した像を造ろうとする努力さえはらわれたほどであった(『長秋記』長承三年(1134)六月十日条)。石部町域には平安末期の仏像が数躯現存するが、これらもまた定朝様の影響をうけるものである。
203040202
長寿寺の諸尊 長寿寺には12世紀の作と目される四躯の影響が存在する。順にながめてみることとしたい。
本堂に向って右奥の場所にある収蔵庫内に安置される阿弥陀如来坐像(重文)は、像高285.5cmの丈六像である。納衣を偏袒右肩に着け、腹前で弥陀の定印を結ぶ姿で肉髺が腕を伏せたようなかたちであること、伏目がちの面貌、衣文線が浅く整えられているなどの点から、12世紀の制作と判断できる。定朝様の系列に属する像ながら、顔の表情をはじめとして全体に洗練を欠く感は否めず、地方作と評すべき作風である。これだけの巨像でありながら、その造立に関する記録は何ひとつ伝わっていない。浄土往生への願いが込められた造像であったろうと想像されるばかりであるが、当初より常行堂ないし阿弥陀堂の主尊として造立されたことは推定できよう。寄木造で、内刳をほどこし、漆箔仕上げとしている。
本堂内にも二躯の平安時代の如来像が安置されている。本尊である子安地蔵の両側に配されているが本来一具の作ではなく、当初の安置場所も他に求められるべきものである。
二躯のうち向って左方の釈迦如来坐像(重文)は像高180.0cmの周丈六像である。右手を胸前のかまえて掌を正面に向け、左手は膝上で迎掌する施無畏・与願の印を結び、納衣を偏袒右肩につけて、左足を外にして坐す。寄木造で内刳、漆箔をほどこす。やはり腕型をした肉髺で、肉取りも抑揚をおさえている。衣文は浅いながらも流麗であり、面相などを見ても、定朝様を踏襲した12世紀の諸仏のなかでも正統的なものであるという感をもつ。ただし、その面部もすでに丸みを失って平板であるのは時代のしからしむるところであろう。
須弥壇上の向って右方には、像高142.5cmの半丈六阿弥陀如来坐像(重文)が安置される。宝印を結び、寄木造、内刳、漆箔をほどこす像である。碗型の肉髺、形式化した衣文せんなど、やはり平安末期の諸像に共通する作風が見出せる。ただ目じりが切れ上がって面貌に一種のさっきが表れているほか、体奥も深さをましており、これらを次代への過渡的な様相と解釈すれば、本像の成立は上記二像よりも遅れ、平安最末期から鎌倉初期にかけてのころではないかと考えられる。なお本像のばあい、後補されがちな台座と光背もほぼ当初のものを伝える点は貴重である。台座は十二方六段魚燐葺の蓮弁をもつ七重蓮華座、光背は周縁部を失うが二重円相光で、外区に透彫で唐草文様を表している。
 |
以上のような大像の遺存は、平安末期の長寿寺の繁栄を物語ってあまりあるものである。いずれも造立の経緯などは判明しないが、収蔵庫の丈六像はむろんのこと、本堂内の釈迦・阿弥陀像にしても、もとは別の堂舎の主尊ではなかったかと推測される。大像造立をささえた往時の長寿寺の経済的な充実を考えるべきであろう。
長寿寺にはさらに一躯の平安仏が存在する。近年までは阿弥陀堂に安置されていた菩薩形立像(県指定)がそれで、明証はないが地元では聖観音とされる。頭上に平安後期に通例の垂髺を結い、天冠台を刻出する。左手を屈して胸前に上げ、右手は垂下し、両手で蓮華の茎のような枝状のものをとるかまえをみせる。眼を伏せた穏やかな表情、楕円形状の大きな腰裳の折返し、静的な姿勢、浅い衣文など、12世紀の菩薩立像として自然である。根幹部は頭・体を通して前後に二材を寄せており、内刳をおこなって、三道下で割首とする技法・構造もこの時代によくみられる。特に強い印象を与える造形ではないが、よく整った美しい像である。本像もその伝来は不詳とするほかない。
203040203
常楽寺の釈迦如来像 長寿寺と並び称される一方の大寺常楽寺は、どちらかといえば中世の遺品に充実しているが、平安時代の作例も少なくない。彫像では本堂の後陣に安置される半丈六の釈迦如来坐像(重文)が存在する。納衣を偏袒右肩に着け、施無畏・与願印を結んで、左足を外にして結跏趺坐する姿である。長寿寺の諸尊に指摘した幾つかの特徴を本像にも認めることができ、やはり12世紀の作と考えられる。ふっくらとした頬の穏やかな表情は、定朝様を踏襲した12世紀の如来像の典型的なものを示しており、きわめて正統的な作風の像である。
次にその構造だが、頭・体を通して根幹部の前面は正中線にて左右二材を寄せ、背面は背板状に三材を矧ぎ、また後頭部にも別材をあてている。注目されるものは、内刳をほどこした像内を平滑に削り、布貼を施したうえ黒漆をとふしている点である。このような手法は決して多くはない。外からは見えない像内には、本像のように像内を入念に仕上げた例としては、金箔を押した万寿寺(京都市東山区)および安楽寿院(京都市伏見区)阿弥陀如来坐像があり、また常楽寺像のように黒漆を塗るものに法金剛院(京都市右京区)や法界寺(京都市伏見区の阿弥陀如来坐像)などがある。いずれも中央の作である点は特に注意されよう。こうしたことはその作風とあいまって、常楽寺釈迦如来像の作者が仏師の直系ではないまでも、その系統につらなる人物であった可能性を示唆するものではないだろうか。残念ながらその作者名を知ることはできないが、右のような推測を可能にするだけの整った造形を示す像であることは確かである。
 |
203040204
そのほかの平安仏 これまでは国および県の指定をうけた諸仏を中心に記述を進めてきたが、石部町域にはそのほかにもまだ未指定の平安時代の仏像がみられる。これらについても述べておきたい。
西福寺(大字石部字西清水・浄土真宗)は明応七年(1498)僧浄斎の開基というが、本尊阿弥陀如来立像は12世紀にさかのぼる古像である。像はその大部分をヒノキの一材から彫出し、内刳を行わない古式の構造をもつ。正面から拝すると、大腿部には刀を入れず、腹部から両脚の間にかけてY字状に衣文を刻出ししている点が目につく。これに類する彫法は平安初期彫刻にもみられるが、それらが大腿部の圧倒的な隆起による自然な衣文であったのに対し、本像の下半身は肉身を感じさせないうすいもので、ただ表面の衣文形式のみをまねているのである。このような手法は平安末期から鎌倉初期にかけて立像には数多くみることができる。像高91.0cmのいわゆる三尺像で、大きさといい作風といい、このようなタイプの阿弥陀立像は在地土豪の持仏堂などに安置礼拝されることが多かったものとかんがえられる。彫法にはやや粗放なところもあり、作者として地方在住の仏師が想定さえよう。
次に善隆寺(大字石部字谷町・浄土宗)の本尊阿弥陀立像も、西福寺像に似たY字状の衣文を刻む像である。その構造は、頭部と体部前面を一材でつくり、これに体部背面・左右両体側部・裳裾背面部にそれぞれ別材を寄せ、さらに両手先・両足先を矧いでいる。しかしその彫法からみて、当初部分は頭部と体部前面をつくる一材のみで、他はすべて後補にかかるものである。頭部に内刳がなく、また頭・体を割り矧いでもいないことから、造像当初は内刳を全くおこなわない一木造の像ではなかったかと推考される。面相部には鼻先をはじめ細かい修補の手が加えられているが、すでに定朝様式とはだいぶん距離がひらき、童顔にちかい可憐な表情となっていることがわかる。このような表情は平安末期から鎌倉初期にかけて、いわゆる藤末鎌初(とうまつけんしょ)の像にときおり見出すことができ、衣文形式や扁平な下半身などもこれに矛盾しない。
善隆寺は石部右馬允家清を本願、覚誉的応を開山として、天正元年(1573)町裏に創建され、貞享元年(1684)、現在の石部城址に移された。寺伝によれば、阿弥陀如来立像は伝教大師の作で、近江源氏佐々木氏より寄進されたという。本願主である石部家清が佐々木義賢(承禎)の家臣であったことや、本像が西福寺像と同様に在地豪族の持仏堂などにまつられるのにふさわしい大きさと作風をもつことなどをおもえば、佐々木氏旧蔵の伝には興味をそそられるものがある。
 |
 |