.jpg)
.jpg) 古代の石部
古代の石部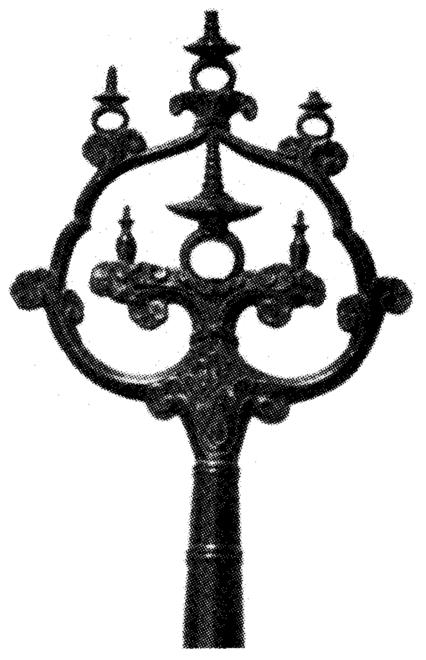
石部南小学校ホームページへ 総合目次へ 郷土歴史はじめへ
総合目次検索へ 石部の自然環境検索へ 古代の石部検索へ 中世の石部検索へ 近世の石部検索へ 近・現代の石部検索へ
200000000
.jpg)
.jpg) 古代の石部
古代の石部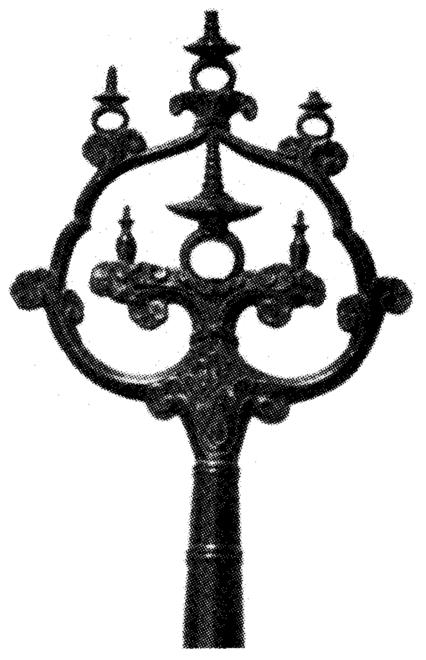
202000000 第二章 奈良時代の石部 (ならじだいのいしべ)
第一節 地方制度の確立 (ちほうせいどのかくりつ)
律令体制の整備 (りつりょうたいせいのせいび)
202010101
公地公民制 大宝元年(701)に制定、その翌年に全面施行された大宝律令によって、わが国古代の律令体制が本格的に始まった。律令体制とは、律・令・格・式などの法令に基づく公地公民制を根幹とする中央集権国家体制をいう。
こうちこうみんせい たいほうがんねん(701)にせいてい、そのよくねんにぜんめんしこうされたたいほうりつりょうによって、わがくにこだいのりつりょうたいせいがほんかくてきにはじまった。りつりょうたいせいとは、りつ・りょう・かく・しきなどのほうれいにもとづくこうちこうみんせいをこんかんとするちゅうおうしゅうけんこっかたいせいをいう。
律令国家が支配する人民を「公民」とよび、戸(家族集団)を編成した。戸ごとの人口台帳である戸籍は、6年ごとに作成し、口分田班給の台帳ともなした。これに対して年々の人口の変動を把握し、徴税の台帳として用いられる計帳は毎年作成される。この戸籍・計帳は国家が公民を個別に支配するための基礎資料であった。
りつりょうこっかがしはいするじんみんを「こうみん」とよび、こかぞくしゅうだん)をへんせいした。こごとのじんこうだいちょうであるこせきは、6ねんごとにさくせいし、くぶんでんはんきゅうのだいちょうともなした。これにたいしてねんねんのじんこうのhげんどうをはあくし、ちょうぜいのだいちょうとしてもちいられるけいちょうはまいねんさくせいされる。このこせき・けいちょうはこっかがこうみんをこべつにしはいするためのきそしりょうであった。
また律令制では、すべての土地は国家の所有する「公地」であり、公民には班田収授法によって口分田を班給した。すなわち6歳以上の良民の男には二段(約23㌃)、女にはその三分の二(1段120歩)を班給し、死後これを収公した。班田は6年に1度行い、受給資格を得た者に口分田を班給し、死亡者の口分田を収公した。
またりつりょうせいでは、すべてのとちはこっかのしょゆうするこうち」であり、こうみんにははんでんしゅうじゅほうによってくぶんでんをはんきゅうした。すなわち6さいいじょうのりょうみんのおとこには2たん(やく23ヘクタール)、おんなにはその3ぶんの21たん120ぶ)をはんきゅうし、しごこれをしゅうこういした。はんでんは6ねんに1どおこない、じゅきゅうしかくをえたものにくぶんでんをはんきゅうし、しぼうしゃのくぶんでんをしゅうこうした。
公民は諸種の租税を負担した。律令制の租税は、大きく分けると、㈠稲穀(租)、㈡物産(調・庸)、⑶力役(雑徭・その他)の三系列になる。
こうみんはしょしゅのそぜいをふたんした。りつりょうせいのそぜいは、おおきくわけると、㈠とうこくそ)、㈡ぶっさんちょう・よう)、⑶りきえき(ぞうよう・そのた)の3けいれつになる。
㈠は土地税で、「租」は口分田一段に対して稲二束二把を課した。租の率は、収穫量の約3%にあたる。春夏に稲を貸し付け、秋に五割ないし三割の利稲を取る「公出率」や、飢饉に備えて戸の等級に応じて栗を徴収する「義倉」も租税とみなされる。
①はとちぜいで、「そ」はくぶんでん1たんにたいしていね2つか2わをかした。そのりつは、しゅうかくりょうのやく3パーセントにあたる。はるなつにいねをかしつけ、あきに5わりないし3わりのりとうをとる「くすいこ」や、ききんにそなえてこのとうきゅうにおうじてくりをちょうしゅうする「ぎそう」もそぜいとみなされる。
㈡は人頭税で、第一に「調」。成年男子に賦課され、正調と副物の二種がある。正調は絹・絁・綿・布などの産物を徴収した。その量は品目によって異なるが、正丁(61~65歳の老丁と軽度の身体障害をもつ正丁)は二分の一、中男(17~20歳)は四分の一の割合で、副物は正丁のみが負担した。なお、京・畿内はそれぞれの半分である。第二に「庸」。本来力役として正丁・次丁に課せられる歳役(正丁10日、次丁五日)の代納物として布・綿・米・塩などを徴収するが、京と畿内は免除された。
②はじんとうぜいで、だい1に「ちょう」。せいじんだんしにふかされ、せちょうとふくぶつの2しゅがある。せちょうはきぬ・あしぎぬ・わた・ぬのなどのさんぶつをちょうしゅうした。そのりょうはひんもくによってことなるが、せいちょう(61~65さいのろうちょうとけいどのしんたいしょうがいをもつせいちょう)は2ぶんの1、ちゅうなんさい)は4ぶんの1のわりあいで、ふくぶつはせいちょうのみがふたんした。なお、きょう・きないはそれぞれのはんぶんである。だい2に「よう」。ほんらいりきえきとしてせいちょう・じちょうにかせられるさいえき(せいちょう10にち、じちょう5にち)のだいのうぶつとしてぬの・わた・もめ・しおなどをちょうしゅうするが、きょうときないはめんじょされた。
⑶もまた成年男子にかかる人頭税で、一年間に正丁60日、次丁30日、中男15日を限度として国司が土木などの労役に駆使した。このほか、50戸1里ごとに正丁2人が徴発されて、在京の諸司の雑役に服する「仕丁」、正丁三人に一人の割合で選ばれて、一部は上京して宮城内・京中の警備にあたる「衛士」、一部は九州の防備にあたる「防人」、それ以外は軍団に交代勤務する「兵士」などがあった。
③もまたせいねんだんしにかかるじおんとうぜいで、1ねんかんにせいちょう60にち、じちょう30にち、ちゅうなん15にちをげんどとしてこくしがどぼくなどのろうえきにくしした。このほか、50こ1りごとにせちょう2にんがちょうはつされて、ざいきょうのしょしのざつえきにふくする「しちょう」、せいちょう3にんに1にんのわりあいでえらばれて、1ぶはじょうきょうしてきゅうじょうない・きょうちゅうのけいびにあたる「えじ」、1ぶはきゅうしゅうのぼうびにあたる「さきもり」、それいがいはぐんだんにこうたいきんむする「へいし」などがあった。
地方行政組織は、国・郡・里の行政単位に分け、それぞれ国司・郡司・里長を置いた。国司は守・介・掾・目の四等官および史生・博士・医師などの雑任からなり、国司の四等官と史生は中央から派遣された。郡司も大領・少領・主政・主帳の四等官からなり、博士・医師および郡司と里長は現地在住者が任用された。
ちほうぎょうせいそしきは、こく・ぐん・りのぎょうせいたんいにわけ、それぞれこくし・ぐんじ・りちょうをおいた。こくしはかみ・すけ・じょう・さかんのよんとうかんおよびししょう・はかせ・くすしなどのぞうにんからなり、こくしのよんとうかんとししょうはちゅうおうからはけんされた。ぐんじもたいりょう・しょうりょう・しゅせい・しゅちょうのよんとうかんからなり、はかせ・くすしおよびぐんじとりちょうはげんちざいにんしゃがにんようされた。
国司の職掌は神祇祭祀、戸籍・計帳の作成、人民の教導、農業の奨励、館内の糺察、土地の管理、訴訟の受理と裁判、租庸調の徴収、官倉の管理、雑徭の徴発、兵士の点定、兵器の管理、駅馬伝馬の管理、僧尼寺院の把握など、地方の行政・警察・裁判・軍事にわたる広範な権限をゆだねられている。これらすべてを10人足らずの国司で執行できるはずはなく、実際は国司の下で各郡の郡司が担当したとみてよい。郡司には大化前代の国造の系譜を引く豪族層が任命されたのは、公民支配に際して旧来の首長に依存する所が大きかったことを意味している。さらに里長は、郡司の下で公民の日常生活を監察し、納税を督促した。
こくしのしょくしょうはじんぎさいし、こせき・けいちょうのさくせい、じんみんのきょうどう、のうぎょうのしょうれい、かんないのきゅうさい、とちのかんり、そしょうのじゅりとさいばん、そようちょうのちょうしゅう、かんそうのかんり、ざつようのちょうはつ、へいしのてんてい、へいきのかんり、うまやてんまのかんり、そうにじいんのはあくなど、ちほうのぎょうせい・けいさつ・さいばん・ぐんじにわたるこうはんなけんげんをゆだねられている。これらすべてを10にんたらずのこくしでしっこうできるはずはなく、じっさいはこくしのしたでかくぶのぐんじがたんとうしたとみてよい。ぐんじにはたいかぜんだいのくにのみやつこのけいふをひくごうぞくそうがにんめいされたのは、こうみんしはいにさいしてきゅうらいのしゅちょうにいそんするところがおおきかったことをいみしている。さらにりちょうは、ぐんじのしたでこうみんのにちじょうせいかつをかんさつし、のうぜいをとくそくした。
202010102
近江国と律令税制 これまでに述べた律令制の租税や地方行政組織の概要を念頭におき、近江国に即してもう少し詳しくみていこう。
おうみこくとりつりょうぜいせい これまでにのべたりつりょうせいのそぜいやちほうぎょうせいそしきのがいようをねんとうにおき、おうみこくにそくしてもうすこしくわしくみていこう。
租は穂つきの稲(頴)で徴収することになっているが、天平年間(729~749)の正税帳によれば、穂から落とした籾(穀)で収納し、そのほとんどを「不動穀」と名付けて備蓄している。地方の財政は公出挙によって賄われているのが実情であった。ただし、特定国の租の一部は米にして、京に運び、諸司官人の食糧にあてた。これを「年料春米」といい、運搬は納税者の負担であった。近江国は都に近いこともあって、年料春米の輸納国に指定されており、『延喜式』には、内蔵寮に50石、民部省に500石、大炊寮に1,200石・糯30石を納める規定となっている。
そはほつきのいね(えい)でちょうしゅうすることになっているが、てんぴょうねんかん(729~749)のしょうぜいちょうによれば、ほからおとしたもみ(こく)でしゅうのうし、そのほとんどを「ふどうこく」となづけてびちくしている。ちほうのざいせいはくすいこによってまかなわれているのがじつじょうであった。ただし、とくていこくのその1ぶはこめにして、きょうにはこび、しょしかんびとのしょくりょうにあてた。これをねんりょうしょうまいといい、うんぱんはのうぜいしゃのふたんであった。おうみこくはみやこにちかいこともあって、ねんりょうしょうまいのゆのうこくにしていされており、『えんぎしき』には、くらりょうに50こく、みんぶしょうに500こく、おおいりょうに1,200こく・もちごめ30こくをおさめるきていとなっている。
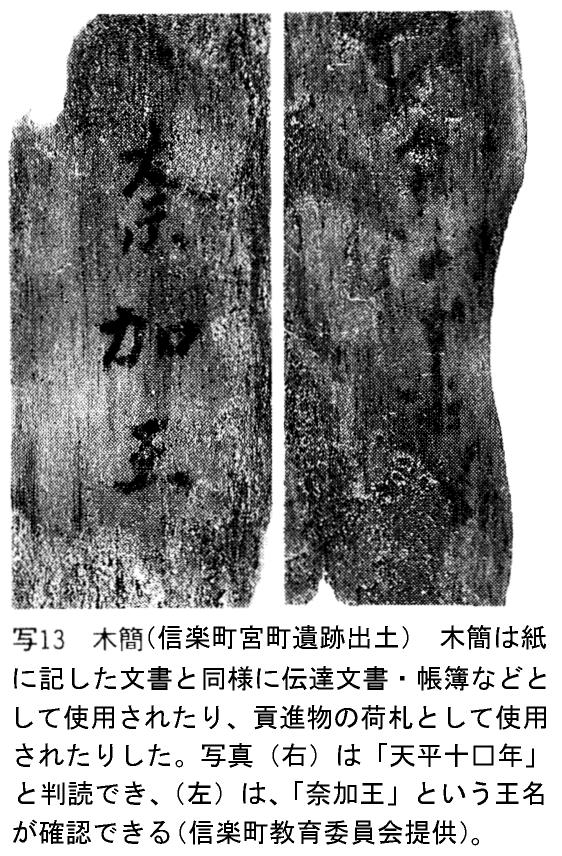 |
律令制では水田が水旱虫霜の害のために五割以上の損失を受けた場合は租を免じ、七割のときは租・調を免じ、八割以上の損害であれば租・調・庸ともに免除する規定だが、実際の運用において一定の範囲以内では国司の裁量に任せた。史書に租税の減免のことが記載されるのは、天災とか国家の慶弔などに際して、特に詔勅を発して租とか調・庸とかを減免した場合に限られ、またこの種の減免は天皇が行幸した途中の国郡に限って行われることもあった。たとえば、延暦二十二年(803)の閏十月、桓武天皇が近江の蒲生野に行幸した時、栗太・甲賀・蒲生の三郡の田租が免除されている(『日本紀略』)。
りつりょうせいではすいでんがすいかんちゅうそうのがいのために5わりいじょうのそんしつをうけたばあいはそをめんじ、7わりのときはそ・ちょうをめんじ、8わりいじょうのそんがいであればそ・ちょう・ようともにめんじょするきていだが、じっさいのうんようにおいていっていのはんいいないではこくしのさいりょうにまかせた。ししょにそぜいのげんめんのことがきさいされるのは、てんさいとかこっかのけいちょうなどにさいして、とくにしょうちょくをはっしてそとかちょう・ようとかをげんめんしたばあいにかぎられ、またこのしゅのげんめんはてんのうがぎょうこうしたとちゅうのこくぐんにかぎっておこなわれることもあった。たとえば、えんりゃく22ねん(803)のうるう10がつ、かんむてんのうがおうみのがもうのにぎょうこうしたとき、くりた・こうか・がもうの3ぐんのでんそがめんじょされている(『にほんきりゃく』)。
調の品目は、絹・絁・糸・綿・布などの繊維品を基本としながらも、雑物といわれる鉄・塩あるいは魚介・海藻類におよぶ郷土の産物であり、庸もまた布・綿・米・塩など郷土の特産物であった。賦役令には調の雑物の例示に「近江の鮒」をあげている。近江国では実際にどのような品目を貢納したか分からないが、『延喜式』には、近江一国が輸納すべき調・庸の品目と数量を、「調二色綾30疋、九点羅2疋、白絹10疋、緑帛20疋、帛130疋、柳筥1合、缶60口、酒壺8合、燼瓮4口、水椀480合、大筥坏1,360口、小筥坏160口、深坏60口、麻笥盤24口、自余は絹を輸せ。韓櫃33合、自余は米を輸せ。中男作物黄蘗300斤、紙、胡麻油、醤鮒、阿米魚鮨、煮塩年魚」と規定している。調庸制の形骸化などで数量は変化したと思われるが、その品目は、湖国の古代の産業を調べるのに参考となるであろう。
ちょうのひんもくは、きぬ・あしぎぬ・いと・わた・ぬのなどのせんいひんをきほんとしながらも、ざつぶつといわれるてつ・しおあるいはぎょかい・かいそうるいにおよぶきょうどのさんぶつであり、ようもまたのの・わた・こめ・しおなどきょうどのとくさんぶつであった。ふえきれいにはちょうのざつもののれいじに「おうみのふな」をあげている。おうみこくではじっさいにどのようなひんもくをくのうしたかわからないが、『えんぎしき』には、おうみいっこくがゆのうすべきちょう。ようのひんもくとすうりょうを、「ちょうにしょくあや30ぴき、きゅうてんら2ひき、しらぎぬ10ぴき、りょくびゃく20ぴき、はく130ぴき、りゅうこ1ごう、かん60こ、さかつぼ8ごう、じんおう4こ、すいわん480ごう、だいきょはい1,360こ、しょうきょはい160こ、しんぱい60こ、あさしゅんばん24こ、じよはきぬをはこばせ。からびつ33ごう、じよはこめをはこばせ。ちゅうなんさくもつおうばく300きん、かみ、ごまあぶら、ひしおのふな、あめうおずし、にしおのあゆ」ときていしている。ちょうようせいのけいがいかなどですうりょうはへんかしたとおもわれるが、そのひんもくは、ここくののこだいのさんぎょうをしらべるのにさんこうとなるであろう。
和銅元年(708)に「和銅開珎」を鋳造した後、蓄銭叙位令を発し、諸国の調・庸を銭納に切りかえるなど、銭貨の流通を促進するための政策を講じたが、そのひとつとして養老六年(722)には近江など畿内に近い八国の調を銭で納めさせている。近江国は京・畿内についで銭貨の流通が期待できたからであろう。このほか、特殊な税制として贄があった。贄とは、朝廷の儀式や天皇の食膳に供される山海の食物で、主として御厨から貢納される。御厨とは、「鵜飼」「江人」「網引」と称する漁民の集団を特定したものであって、彼らは水産物を贄として貢納する代わりに調として雑徭が免じられている(『令集解』)。近江国には栗太郡の勢多、滋賀郡の和邇、坂田郡の筑紫に御厨が、栗太郡の田上に御網代があって、琵琶湖および瀬田川の年魚(鮎)・鮒・鱒・阿米魚(雨魚、ビワマスの別称)・氷魚などを漁獲し、これを贄として貢進したのである。
わどうがんねん(708)に「わどうかいちん」をちゅうどうしたのち、ちくせんじょいれいをはっし、しょこくのちょう・ようをせんのうにきりかえるなど、せんかのりゅうつうをそくしんするためのせいさくをこうじたが、そのひとつとしてようろう6ねん(722)にはおうみなどきないにちかい8こくのちょうをぜにでおさめさせている。おうみこくはきょう・きないについでせんかのりゅうつうがきたいできたからであろう。このほか、とくしゅなぜいせいとしてにえがあった。にえとは、ちょうていのぎしきやてんのうのしょくぜんにきょうされるさんかいのしょくもつで、しゅとしてみくりやからくのうされる。みくりやとは、「うかい」「えびと」「つなひき」としょうするぎょみんのしゅうだんをとくていしたものであって、かれらはすいさんぶつをにえとしてくのうするかわりにちょうとしてざつようがめんじられている(『りょうのしゅうげ』)。おうみこくにはくりたぐんのせた、しがぐんのわに、さかたぐんのつくしにみくりやが、くりたぐんのたなまきにおあじろがあって、びわこおよびせたがわのあゆ(あゆ)・ふな・ます・あめうお(あめうお、、ビワマスのべっしょう)・ひうおなどをぎょかくし、これをにえとしてこうしんしたのである。
 |
 |