.jpg)
.jpg) 古代の石部
古代の石部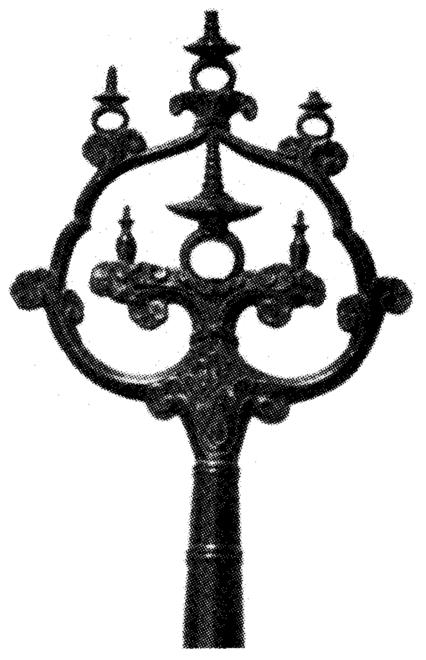
石部南小学校ホームページへ 総合目次へ 郷土歴史はじめへ
総合目次検索へ 石部の自然環境検索へ 古代の石部検索へ 中世の石部検索へ 近世の石部検索へ 近・現代の石部検索へ
200000000
.jpg)
.jpg) 古代の石部
古代の石部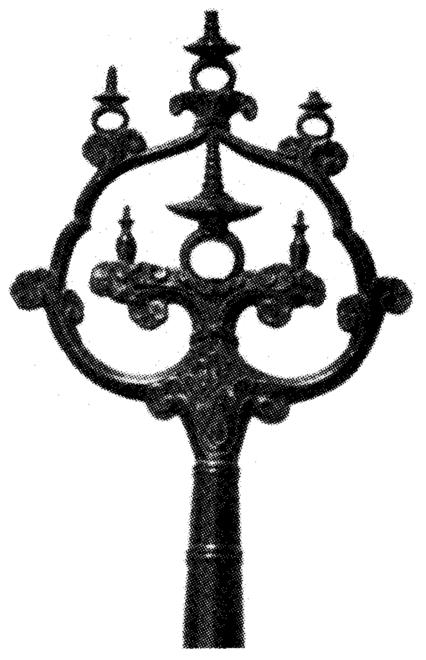
203000000 第三章 平安時代の石部
203020000
第二節 伊勢路と石部駅館
石部駅家
203020301
石部の宿的機能の初出 伊勢勅使の記載の中で石部に関して最も注目されてる文献は、『雅実公記』の記述である。この日記は、保安三年(1122)に源氏で初めて太政大臣となって源雅実の手になるものである。これは、雅実が家号を久我といったので『久我相国記』とも呼ばれている。
雅実は、長治二年(1105)八月十三日伊勢勅使として京都を出発し「勢田」に到着、十五日「甲可」、十六日「鈴鹿」、十七日「壱志、十八日には「伊勢」に至っている。このルートは、ほとんど「権記」にしるされているそれと変わらない旅程である。二十日には帰路に着き、「壱志驛」に泊り、二十一日「関驛家」、翌二十二日鈴鹿峠を越えた一行は、「甲可」に泊らず「石部驛家」で近江国司の出迎えを受け、そこで宿泊しているのである。この記事が石部の宿的機能を示す初めての史料である。翌二十三日には、一行は京都へ到着した。嘉承二年(1107)二月十一日、再び伊勢勅使として京都を出発した雅実は、「勢多驛」に入り、翌十二日に「石部驛家」に至る。十三日には石部を出発し、一気に鈴鹿峠を越え「関驛家」に到着している。十三日(この日)の行程はかなり強行軍であったらしく、「山嶮道遠、人疲馬泥」としるしている。
伊勢に着いた一行は、十七日に伊勢を出発して「壱志驛」、十八日「関驛」、十九日「石部驛館」についている。
この瀬田から甲賀に泊らず石部に宿泊し、鈴鹿峠を越え、関に至るルートの中にはかなりの難所があった。甲賀駅家を利用して関に至る行程は、朝八時に出発し、夜五時に到着するのが一般的であるのに対し、石部に泊った場合夜七時に関へ到着しており、二時間あまりの時間を費やしている。
203020302
石部駅家をめぐる課題 石部駅家は、『雅実公記』にしか「石部駅家」の記載がみられず詳しいことは不明であるが、伊勢勅使が宿泊する「假屋」・「借家」の施設があったものと考えられる。『帥記』には、「鈴鹿駅」に「借家卅宇」があることを記しており、かなりの規模の宿泊施設が存在していたことが推察できる。
永久二年(1114)二月十日に伊勢勅使として出発した藤wら宗忠が記した『忠右記』では、勢田から甲賀駅家に宿泊しており、石部の記述はみられない。しかしながら、一時期であっても石部に伊勢勅使の宿泊施設が設置されていたことは、交通の要所として重要な位置にあったことを示しているといえよう。
また、これらの日記の中に、『延喜式』に記された岡田駅家の記載がみられない。このことは甲賀駅家以外の栗田駅家・石部駅家などの宿泊施設が存在したことと何らかの関係があるのではなかろうか。残された課題として指摘しておきたい。
 |
 |